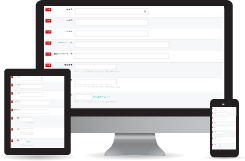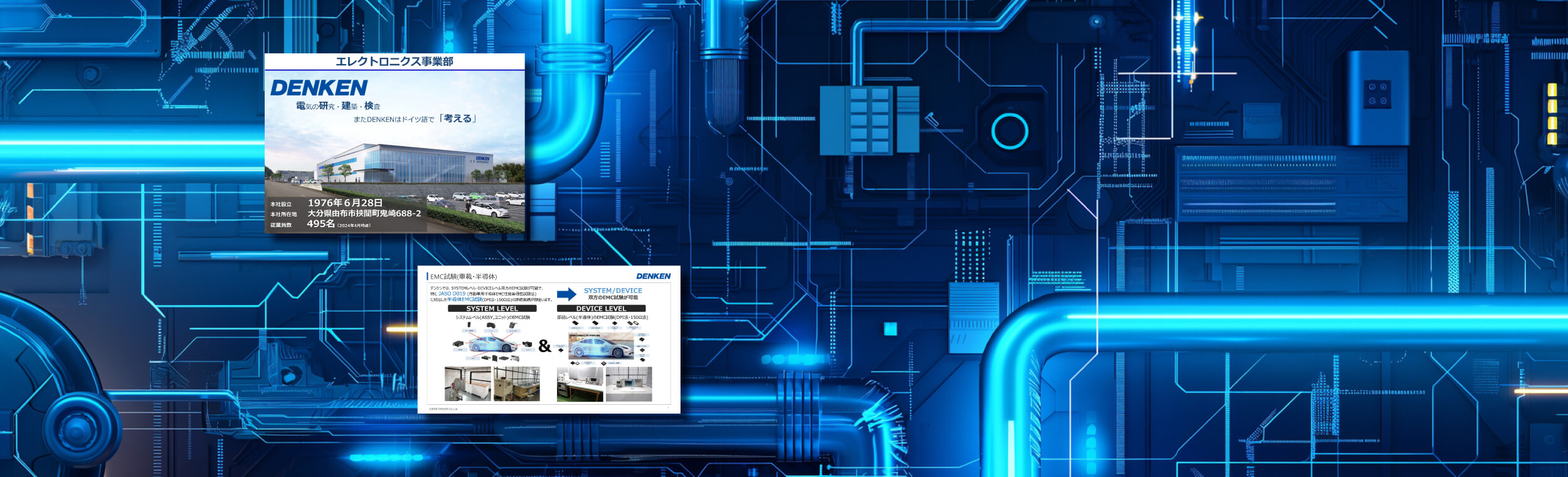EMC試験の基本を解説! エミッションとイミュニティの違いとは
電子機器の開発・製造において、その安全性と信頼性を確保するために欠かせないのが「EMC試験」です。EMC試験については「必要なのはわかるけれど、詳しい内容はよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、愛知県刈谷市にあるIEC/ISO認定試験場「デンケン中部センター」の技術スタッフに、EMC試験の基本的な分類である「エミッション」と「イミュニティ」について、わかりやすく解説していただきました。
[この記事でわかること]
・EMC試験の基本的な2種類「エミッション試験」と「イミュニティ試験」
・それぞれの試験方法と評価内容
・「放射」と「伝導」の違い
・EMC試験に関連するその他の試験
EMCとは「電磁両立性」の略称です
まず、「EMC」とは「Electromagnetic Compatibility」の頭文字を取った略称で、日本語では「電磁両立性」と訳されます。ここでいう「両立性」とは、電子機器に関する2つの重要な特性を同時に満たすという意味です。

エミッションとイミュニティ EMC試験で確認する2つの重要事項
EMC試験では、主に次の2点を確認します。
- 影響をあたえない …… 製品から発生する電磁波・ノイズが他の機器に影響を与えないか ⇒エミッション試験
- 影響をうけない …… 製品が外部からの電磁波・ノイズの影響を受けて誤動作しないか ⇒イミュニティ試験
この2つの特性を両立させることで、複数の電子機器が同じ環境で安全に動作できるようにするのがEMC試験の目的です。
自動車を例に考えると、カーナビやオーディオ、エアコン制御など様々な電子機器が搭載されていますが、これらが互いに干渉せず、また外部からの電磁波(例:高圧送電線の近くや無線基地局付近)にも影響されずに正常に動作する必要があります。
では、EMC試験の2つの基本カテゴリーを詳しく見ていきましょう。
エミッション試験:「影響を与えない」ことを確認
エミッション試験は、「製品から発生する電磁波が他の製品に影響を与えないか」を確認する試験です。製品から発生するノイズ(不要な電磁波)が規格で定められた閾値(しきいち)を超えていないかを測定します。
エミッション試験は、ノイズの伝わり方によって、さらに2つに分類されます。
・放射エミッション試験
「放射エミッション」は、製品から空間を通じて放射される電磁波を測定する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用状態で動作させ、規格に則って周波数帯に合わせたアンテナを設置します。そしてレシーバーやスペクトラムアナライザーなどの測定機器を用いて、規格で定められた閾値を超えるノイズが出ていないかどうかを確認します。

放射エミッション試験のアンテナ設置例
・伝導エミッション試験
「伝導エミッション」は、電線やケーブルなどを経由して伝わる電磁波を測定する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、製品のケーブルに電流プローブや電圧プローブを接続します。そしてレシーバーやスペクトラムアナライザーなどの測定機器を使って、規格で定められた閾値を超えるノイズが出ていないかどうかを確認します。

伝導エミッション試験で使用する電流プローブの例
イミュニティ試験:「影響を受けない」ことを確認
イミュニティ試験では、「製品が外部からの電磁波の影響を受けて誤動作しないか」を確認します。製品に意図的にノイズを与え、製品の耐性を評価します。
イミュニティ試験も、ノイズの伝わり方によって2つに分類されます。
・放射イミュニティ試験
「放射イミュニティ」は、空間を通じて伝わる電磁波に対する製品の耐性を確認する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、アンテナから意図的に電磁波(ノイズ)を放射します。製品が誤動作しないことを確認します。一般的には、最も厳しいレベル(例:レベル4)から試験を開始し、製品がそのレベルでパスすれば合格となります。パスしなかった場合は、レベルを下げて再試験を行います。

放射イミュニティ試験で使用するアンテナの例
・伝導イミュニティ試験
「伝導イミュニティ」は、電線やケーブルを通じて伝わるノイズに対する製品の耐性を確認する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、電流プローブなどを使って、製品のケーブルに意図的にノイズを注入し、製品が誤動作しないことを確認します。放射イミュニティ試験と同様に、一般的には最も厳しいレベルから試験を開始し、合否を判定します。

伝導イミュニティ試験で使用する電流プローブの例
その他のEMC関連試験
EMCの基本的な試験である「エミッション」と「イミュニティ」に加えて、特定の電気的特性を確認するための試験もあります。デンケンでは以下のような試験も実施可能です。
- 雷サージ試験:雷による過電圧の影響を確認する試験
- ファストトランジェントバースト試験:スイッチング動作などで発生する高速なノイズの影響を確認する試験
- 静電気放電試験:静電気による影響を確認する試験
これらの試験は、製品の使用環境に応じて必要となる場合がありますので、具体的な試験内容についてはお問合せからご相談ください。
まとめ
この記事では、EMC試験の基本的な2つのカテゴリー「エミッション」と「イミュニティ」について解説しました。
[この記事のポイント]
・EMCとは「電磁両立性」の略で、「影響を与えない」と「影響を受けない」という2つの特性を両立させること
・エミッション試験は「放射」と「伝導」の2種類があり、製品から発生するノイズが規格の閾値を超えないことを確認する
・イミュニティ試験も「放射」と「伝導」の2種類があり、外部からのノイズに対する製品の耐性を確認する
デンケン中部センターでは、規格に基づいたEMC試験を提供しており、試験室の空き状況はオンラインで確認できます。EMC試験に関するご相談や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
デンケンEMC試験所 試験日程表
https://dkn-emc.jp/top
※2回目以降はオンライン予約も可能です
初回予約の方法
電話 0566-95-2170
お問合せ先 https://www.dkn.co.jp/contact/
教えてくれた人

デンケン中部センター 杉浦 貴紀
デンケン中部センターの杉浦です。このブログでは当サイトでの試験情報についてご紹介していきますのでよろしくお願いします。
この記事を書いた人

ものづくりライター 新開 潤子
製造業専門で執筆活動を行う「ものづくりライター」。ものづくりについて広く知識を持ち、ものづくり技術を言葉で表現して伝える活動を、愛知県を拠点に展開中。
https://office-kiitos.biz/
電子機器の開発・製造において、その安全性と信頼性を確保するために欠かせないのが「EMC試験」です。EMC試験については「必要なのはわかるけれど、詳しい内容はよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、愛知県刈谷市にあるIEC/ISO認定試験場「デンケン中部センター」の技術スタッフに、EMC試験の基本的な分類である「エミッション」と「イミュニティ」について、わかりやすく解説していただきました。
| [この記事でわかること] ・EMC試験の基本的な2種類「エミッション試験」と「イミュニティ試験」 ・それぞれの試験方法と評価内容 ・「放射」と「伝導」の違い ・EMC試験に関連するその他の試験 |
EMCとは「電磁両立性」の略称です
まず、「EMC」とは「Electromagnetic Compatibility」の頭文字を取った略称で、日本語では「電磁両立性」と訳されます。ここでいう「両立性」とは、電子機器に関する2つの重要な特性を同時に満たすという意味です。

EMC試験で確認する2つの重要事項
EMC試験では、主に次の2点を確認します。
- 影響をあたえない …… 製品から発生する電磁波・ノイズが他の機器に影響を与えないか ⇒エミッション試験
- 影響をうけない …… 製品が外部からの電磁波・ノイズの影響を受けて誤動作しないか ⇒イミュニティ試験
この2つの特性を両立させることで、複数の電子機器が同じ環境で安全に動作できるようにするのがEMC試験の目的です。
自動車を例に考えると、カーナビやオーディオ、エアコン制御など様々な電子機器が搭載されていますが、これらが互いに干渉せず、また外部からの電磁波(例:高圧送電線の近くや無線基地局付近)にも影響されずに正常に動作する必要があります。
では、EMC試験の2つの基本カテゴリーを詳しく見ていきましょう。
エミッション試験:「影響を与えない」ことを確認
エミッション試験は、「製品から発生する電磁波が他の製品に影響を与えないか」を確認する試験です。製品から発生するノイズ(不要な電磁波)が規格で定められた閾値(しきいち)を超えていないかを測定します。
エミッション試験は、ノイズの伝わり方によって、さらに2つに分類されます。
・放射エミッション試験
「放射エミッション」は、製品から空間を通じて放射される電磁波を測定する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用状態で動作させ、規格に則って周波数帯に合わせたアンテナを設置します。そしてレシーバーやスペクトラムアナライザーなどの測定機器を用いて、規格で定められた閾値を超えるノイズが出ていないかどうかを確認します。

放射エミッション試験のアンテナ設置例
・伝導エミッション試験
「伝導エミッション」は、電線やケーブルなどを経由して伝わる電磁波を測定する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、製品のケーブルに電流プローブや電圧プローブを接続します。そしてレシーバーやスペクトラムアナライザーなどの測定機器を使って、規格で定められた閾値を超えるノイズが出ていないかどうかを確認します。

伝導エミッション試験で使用する電流プローブの例
イミュニティ試験:「影響を受けない」ことを確認
イミュニティ試験では、「製品が外部からの電磁波の影響を受けて誤動作しないか」を確認します。製品に意図的にノイズを与え、製品の耐性を評価します。
イミュニティ試験も、ノイズの伝わり方によって2つに分類されます。
・放射イミュニティ試験
「放射イミュニティ」は、空間を通じて伝わる電磁波に対する製品の耐性を確認する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、アンテナから意図的に電磁波(ノイズ)を放射します。製品が誤動作しないことを確認します。一般的には、最も厳しいレベル(例:レベル4)から試験を開始し、製品がそのレベルでパスすれば合格となります。パスしなかった場合は、レベルを下げて再試験を行います。

放射イミュニティ試験で使用するアンテナの例
・伝導イミュニティ試験
「伝導イミュニティ」は、電線やケーブルを通じて伝わるノイズに対する製品の耐性を確認する試験です。
・試験方法:
製品を通常使用する状態で動作させ、電流プローブなどを使って、製品のケーブルに意図的にノイズを注入し、製品が誤動作しないことを確認します。放射イミュニティ試験と同様に、一般的には最も厳しいレベルから試験を開始し、合否を判定します。

伝導イミュニティ試験で使用する電流プローブの例
その他のEMC関連試験
EMCの基本的な試験である「エミッション」と「イミュニティ」に加えて、特定の電気的特性を確認するための試験もあります。デンケンでは以下のような試験も実施可能です。
- 雷サージ試験:雷による過電圧の影響を確認する試験
- ファストトランジェントバースト試験:スイッチング動作などで発生する高速なノイズの影響を確認する試験
- 静電気放電試験:静電気による影響を確認する試験
これらの試験は、製品の使用環境に応じて必要となる場合がありますので、具体的な試験内容についてはお問合せからご相談ください。
まとめ
この記事では、EMC試験の基本的な2つのカテゴリー「エミッション」と「イミュニティ」について解説しました。
[この記事のポイント]
・EMCとは「電磁両立性」の略で、「影響を与えない」と「影響を受けない」という2つの特性を両立させること
・エミッション試験は「放射」と「伝導」の2種類があり、製品から発生するノイズが規格の閾値を超えないことを確認する
・イミュニティ試験も「放射」と「伝導」の2種類があり、外部からのノイズに対する製品の耐性を確認する
デンケン中部センターでは、規格に基づいたEMC試験を提供しており、試験室の空き状況はオンラインで確認できます。EMC試験に関するご相談や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
デンケンEMC試験所 試験日程表
https://dkn-emc.jp/top
※2回目以降はオンライン予約も可能です
初回予約の方法
電話 0566-95-2170
お問合せ先 https://www.dkn.co.jp/contact/
教えてくれた人
 | デンケン中部センター 杉浦 貴紀 デンケン中部センターの杉浦です。このブログでは当サイトでの試験情報についてご紹介していきますのでよろしくお願いします。 |
この記事を書いた人
 | ものづくりライター 新開 潤子 製造業専門で執筆活動を行う「ものづくりライター」。ものづくりについて広く知識を持ち、ものづくり技術を言葉で表現して伝える活動を、愛知県を拠点に展開中。 https://office-kiitos.biz/ |